お役立ち情報
クリニックにおける人事・労務の問題とトラブル回避術
クリニック経営において欠かせない「人事・労務管理」。しかし、医療現場特有の課題として、職種ごとの待遇差や労働時間管理の複雑さ、スタッフの離職率といった問題が山積していませんか?
「突然の退職で人手が足りない」「スタッフ同士のトラブルが絶えない」といった状況が続くと、医療サービスの質にも影響しかねません。
本記事では、クリニックが抱える人事・労務の問題点を整理し、トラブルを未然に防ぐための実践的な回避術を詳しく解説します。安定した労務管理を実現し、スタッフ定着率を向上させるためのヒントをぜひお役立てください。
クリニックの人事・労務の問題とは?
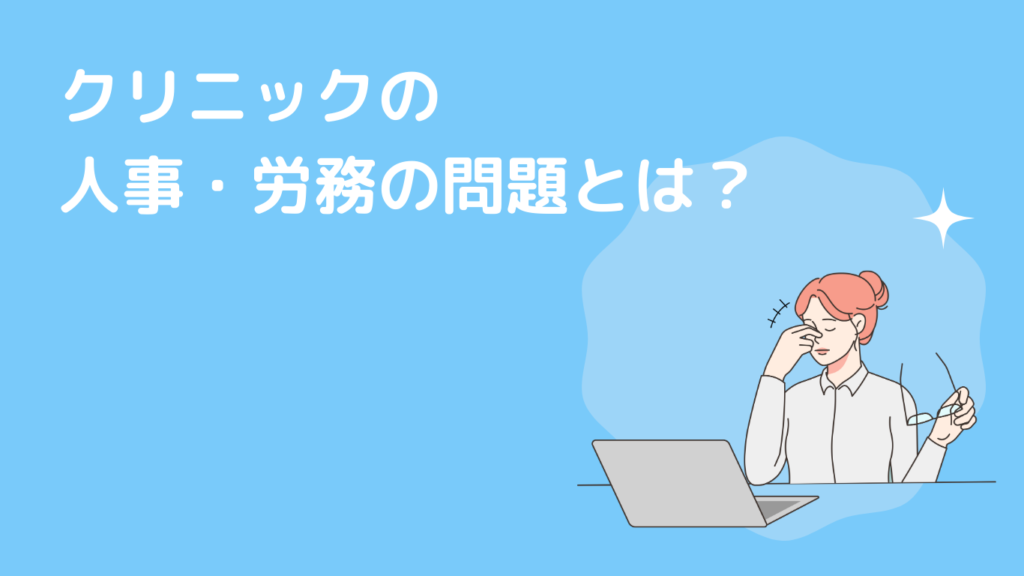
クリニック経営では、人事・労務管理が複雑になりやすいと言われています。医療現場特有の職種の多様性や労働環境の問題が絡み合い、スタッフの不満やトラブルが生じやすい状況が続いているからです。
人材の定着とスムーズな職場運営を実現するためには、まずクリニック特有の労務問題の現状をしっかり把握することが重要です。
医療業界の入職率・離職率の実態
医療業界の入職率と離職率は、産業全体と比較してやや高い傾向にあります。理由の一つは、資格や経験を活かせる医療業界では、転職が比較的容易であることです。
〈業界データ〉
- 医療・福祉業界の平均離職率:15%
→ 年間100人中15人が離職する計算です。 - クリニックの場合:規模が小さいため、7人に1人が離職している計算となり、人員の入れ替わりが目立ちやすい傾向があります。
参考:日本医事新報社HP
クリニックの労務問題の例
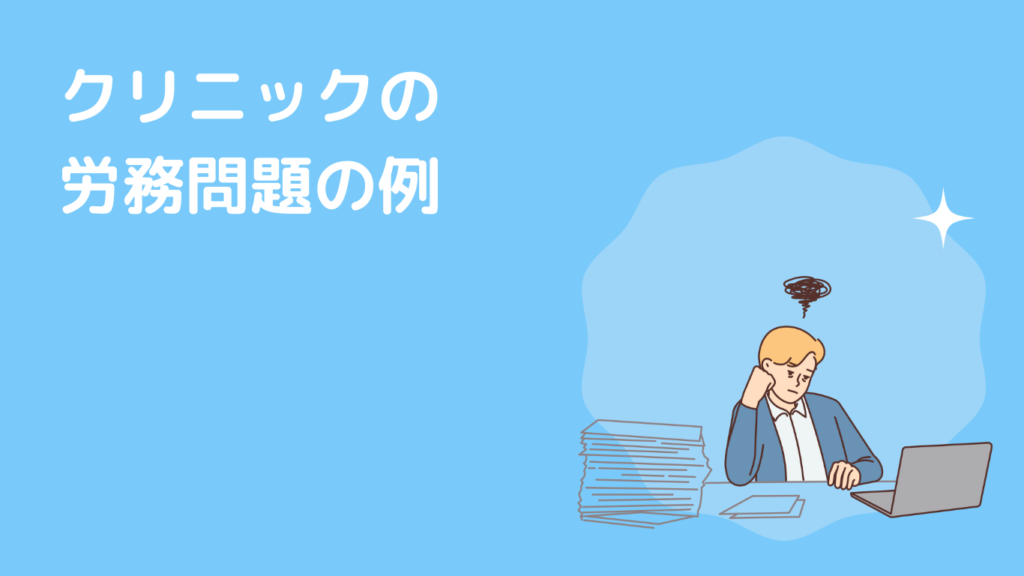
クリニックでは、一般企業と比べて労務問題が発生しやすい傾向にあります。
以下では、代表的な労務問題について詳しく解説します。
突然の退職・休職
クリニックは、女性スタッフが多い職場です。出産や家庭の事情、配偶者の転勤など、ライフイベントを理由に突然の退職や休職が発生しやすい環境といえます。小規模なクリニックでは、一人でも欠けると業務に大きな影響が出てしまいます。
たとえば、受付クラークや技師が1名体制で業務を回していた場合、そのスタッフが休職することで診療が進まなくなるケースも少なくありません。こうした状況を放置しておくと、スタッフの不安や不満が増大し、さらなる離職を招く恐れもあります。
職種の異なるスタッフが混在している
クリニックには、医師、看護師、医療事務、理学療法士など、さまざまな職種が集まっています。それぞれの役割や働き方が異なるため、労務管理が複雑になるのはもちろん、待遇や評価に対する不満が生じやすい環境ともいえます。
同じ職種であっても、常勤とパートの労働条件や給与に違いがある場合、スタッフ間で「不公平感」を抱きやすくなります。こうした小さな不満が放置されると、職場の人間関係が悪化し、職種ごとに派閥が生まれることもあります。
また、業務内容や負担のばらつきも問題です。たとえば、看護師と医療事務では患者対応や責任の重さが異なり、互いの業務負担を理解し合えないことで摩擦が生じるケースがあります。
残業など労働時間管理
クリニックでは、診療時間が固定されている一方で、患者対応や突発的な業務が発生しやすいため、残業が常態化しやすい状況があります。
特に終業間際に患者が来院すると、看護師や医療事務スタッフはその対応に追われ、予定外の労働が発生します。曜日や時間帯によって診療終了時刻が変動することも多く、労働時間の把握が難しいケースが少なくありません。
また、残業代の未払いがトラブルの引き金となることもあります。「サービス残業」が常態化している職場では、スタッフの不満が溜まりやすく、離職率が高くなる傾向が見られます。
勤務シフトの多様性と管理
クリニックでは、午前と午後に分かれた診療時間に合わせて働くスタッフも多く、勤務シフトが複雑化しやすい特徴があります。これにより、シフトの調整が難しくなるだけでなく、シフトが不均衡になることで業務負担が偏ることも少なくありません。
月ごとにシフトを調整する場合も、急な欠勤や退職が重なると対応が追いつかず、シフトの穴埋めに常勤スタッフの負担が増えることがよくあります。
専門職の代替人員の不足
クリニックは最低限の人数で運営されていることが多く、特に看護師や技師、受付クラークといった専門職の役割は一人ひとりの負担が大きいのが現状です。
こうした専門職が急な退職や休職をすると、代わりの人員を確保するのが難しいことが少なくありません。特に地方や小規模なクリニックでは、人材不足がより深刻な課題となります。
例えば、看護師が1名しかいない状況で休職に入ると、診療のサポート業務が滞り、他のスタッフがカバーしきれない場合もあります。結果として、残ったスタッフの負担が増加し、職場全体の疲弊につながります。
労働条件に敏感なスタッフへの対応
クリニックでは、労働条件への不満がスタッフの離職やトラブルの引き金になることが少なくありません。特に医療現場のスタッフは、給与や手当、勤務時間などの待遇に敏感であり、他の職場との比較によって不満が顕在化しやすい傾向があります。
例えば、職員同士で給与や手当について話題にする機会があると、「自分の待遇は不公平ではないか」と感じるスタッフが現れることがあります。こうした不満が正当な主張であれば対応が必要ですが、放置してしまうと職員同士の不信感が高まり、労務トラブルへと発展しかねません。
また、労働条件への不満は時に「正義感」と結びつくこともあります。同僚の待遇が不適切だと感じた場合、当事者ではないスタッフが改善を求めるケースもあり、職場全体の問題として広がることもあります。
こうした状況が長引くと、「院長対スタッフ全員」という対立構図が生まれ、最悪の場合、労働紛争に発展するリスクもあります。職場全体の雰囲気を悪化させないためにも、労働条件への敏感さを理解し、適切な対応を心掛けることが重要です。
クリニックの労務管理が難しい理由
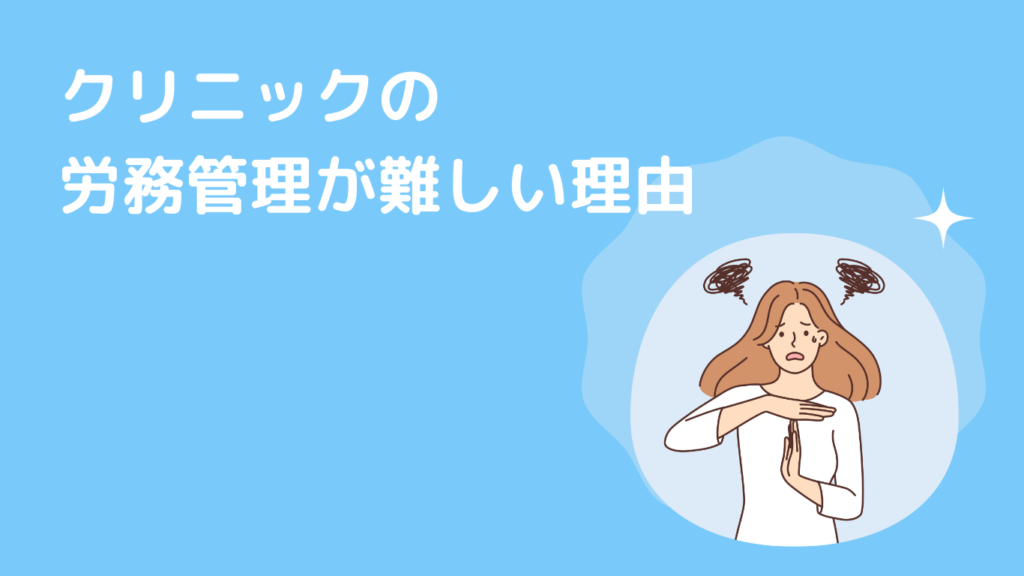
クリニックの労務管理が難しいとされる背景には、医療業界特有の要因があります。管理者が抱える多忙な業務や、多職種のスタッフが混在する環境などが影響し、労働環境の管理が複雑化しやすいのです。
ここでは、クリニックにおける労務管理が難しいとされる具体的な理由について解説します。
管理者の労務管理や労働法に関する知識不足
クリニックの管理者である院長先生は、医療の専門家であり診療業務に日々忙しく取り組んでいます。しかし、経営者としての労務管理や労働法に関する知識については十分にカバーされていないケースが少なくありません。
医療法や健康保険法といった医療関連の法律は遵守していても、労働基準法や労働時間管理についての理解が不足しがちです。たとえば、
・残業代の未払い
・法定労働時間の超過
など、知らないうちに違反行為となっていることもあります。
大きな病院では、労務管理に詳しい事務局や担当者が配置されることが一般的ですが、クリニックではそうした体制が整っていないことがほとんどです。そのため、労務管理の問題が後回しになり、スタッフの不満やトラブルへとつながってしまいます。
職種ごとの労働条件・待遇の複雑さ
クリニックには、医師、看護師、医療事務、歯科衛生士、理学療法士など、複数の職種が働いています。それぞれの職種には役割や業務内容に違いがあり、労働条件や待遇を一律に管理することが難しくなります。
たとえば、
- 看護師と医療事務では業務負担や責任の重さが異なる
- 常勤職員とパート職員では給与や福利厚生が大きく異なる
こうした違いから、スタッフ同士で待遇の比較が起こりやすく、不公平感を感じることで不満が生まれることがあります。さらに、評価基準が曖昧な場合、職員間での信頼関係が揺らぎ、業務効率にも影響する恐れがあります。
職種ごとに求められるスキルや経験が異なる以上、待遇や労働条件に違いが生じるのは自然なことです。しかし、明確な基準やルールがないまま放置すると、職場全体に不和が広がり、離職率の増加につながることも少なくありません。
労働時間の管理体制の不備
クリニックでは、患者対応や突発的な業務が発生しやすく、労働時間の管理が曖昧になることが多く見られます。診療時間が決まっていても、終業時間間際の患者対応や事務作業の残りにより、スタッフの勤務時間が自然と延びてしまうケースが少なくありません。
特に、以下のような状況が労働時間管理を難しくしています。
- 診療が予想以上に長引くことで、定時を超えた業務が常態化する
- 休憩時間が確保できないまま業務が続く
- タイムカードが正確に管理されておらず、残業代が支払われない
これらの不備が放置されると、スタッフの不満が高まり、サービス残業や労働基準法違反などの問題に発展する恐れがあります。また、正確な労働時間を記録しないことで、経営者側が気付かないうちに法的なリスクを抱えることにもなります。
スタッフの帰属意識や経営者意識の不足
クリニックでは、管理者である医師が診療の中心となるため、スタッフにとって「経営者」としての院長の存在は意識されにくいことがあります。その結果、スタッフの帰属意識や経営者意識が希薄になりがちです。
スタッフが帰属意識を持てない背景には、以下のような要因が考えられます。
- 医師が忙しく、スタッフとのコミュニケーションが不足している
- 職場のルールや評価基準が曖昧で、自分の役割や貢献度が見えにくい
- 経営側と現場スタッフの間に距離があり、クリニック全体としての一体感が生まれにくい
経営意識の不足は、スタッフのモチベーション低下につながり、「ここで働き続けたい」と感じにくい環境を生み出します。例えば、クリニック全体の目標や方針が共有されていない場合、スタッフは「単なる労働者」としての意識に留まり、経営の一員としての意識が育ちません。
労務管理が整うことで得られる3つのメリット

労務管理が整うことで、クリニックの経営やスタッフの働きやすさに大きなメリットをもたらします。労務管理の適正化は、スタッフのモチベーション向上や労働環境の改善、経営の安定化にも直結するため、見直しと改善が非常に重要です。
ここでは、労務管理が整うことで得られる3つの具体的なメリットについて解説します。
1.労働条件の明確化でスタッフのモチベーション向上
クリニックでは、給与や労働時間、福利厚生などの労働条件が曖昧な場合、スタッフの不満が生じやすくなります。しかし、労務管理を適正化し、労働条件を明確にすることで、スタッフのモチベーションは大きく向上します。
例えば、残業代の支払いや休憩時間の確保、評価制度の明示など、働く上でのルールや待遇が明確になることで、スタッフは安心感を持って業務に集中できるようになります。「自分の働きが正当に評価されている」と感じることで、モチベーションの向上にもつながり、離職率の低下にも貢献します。
2.労働環境の安定が経営の安定化につながる
労務管理が整い、労働環境が安定すると、スタッフの定着率が高まり、経営も安定します。労働条件の不透明さや人間関係のトラブルが原因で離職が続くと、クリニックの運営に大きな支障が出てしまいます。
例えば、突然の退職や休職によって人員が不足すると、残ったスタッフに業務が集中し、過度な負担が生じる悪循環に陥ることがあります。しかし、適切なシフト管理や労働時間の把握を行い、スタッフが安心して働ける環境を整えることで、労働力の安定が確保され、クリニック全体の生産性も向上します。
3.不祥事への対応が正当化される
労務管理が整備されていないクリニックでは、不祥事が発生した際に対応が曖昧になりがちです。スタッフの処分や解雇を巡ってトラブルが発生し、労働紛争に発展するケースも少なくありません。
しかし、労務管理を適正に行い、就業規則や評価基準を明確にしておくことで、不祥事が発生した際の対応が正当化されます。たとえば、無断欠勤や重大な医療ミスがあった場合でも、ルールに基づいて処分を行えば、不当解雇として訴えられるリスクを回避できます。
人事・労務の問題の施策
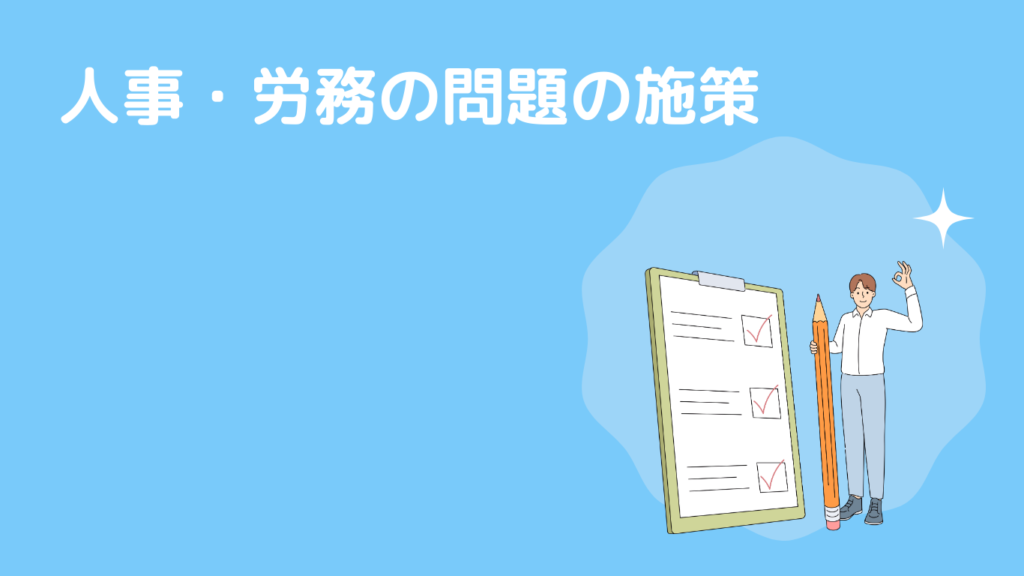
クリニックでは、医療業界特有の労務管理の難しさから離職率が高くなりやすい傾向にあります。優秀な人材を確保し、長く働き続けてもらうためには、採用と定着の両面から施策を講じることが欠かせません。
ここでは、クリニックの現状を見直しながら、採用・定着率を改善するための具体的な施策を紹介します。
採用プロセスの最適化
医療業界における採用活動では、医療職特有の資格や経験の重要性を踏まえた工夫が求められます。そのため、採用プロセスの最適化が欠かせません。募集方法を見直し、医療業界専門の求人サイトや紹介会社を活用して、ターゲットとなる人材に適した媒体を選ぶことがポイントです。
また、採用基準を明確にすることで、求める人材像を具体的に定義し、スキルや経験だけでなく働き方に合った基準を設けることができます。面接においては、業務内容や職場の雰囲気を正確に伝え、入職後のギャップを減らすためのコミュニケーションを重視することが重要です。
さらに、働きやすい環境づくりやキャリア支援といった差別化ポイントを採用段階で積極的にアピールすることで、他のクリニックとの差別化が図れます。
職場環境の改善
採用活動だけでなく、スタッフが長く働き続けられる環境を整備することは、医療現場の安定運営において欠かせません。特に、医療の現場では業務負担が大きくなりやすいため、職場環境の改善がスタッフの定着率向上に直結します。まず、労働条件を見直し、残業の抑制や労働時間の適切な管理、さらに給与や福利厚生の充実を図ることが重要です。
就業規則の作成と見直し
クリニックにおける労務管理の第一歩は、就業規則の作成と見直しです。働く上でのルールが不明確な状態では、スタッフが不安を感じやすく、労務トラブルの温床にもなりかねません。
特に10人以上のスタッフを抱えるクリニックでは、法律上の義務として就業規則が必要です。しかし、10人未満の場合でも、労働条件や勤務ルールを明確に定めることで、トラブルの予防や職場の秩序維持に役立ちます。
また、就業規則は一度作成して終わりではありません。クリニックの成長やスタッフ数の増加、労働環境の変化に応じて定期的に見直し、現状に即した内容に更新していくことが求められます。
労働時間の適正管理
クリニックでは、診療時間や患者の状況に応じて業務が長引くことが多く、労働時間の管理が曖昧になりがちです。特に残業時間が常態化してしまうと、スタッフの負担が増大し、不満や離職の原因にもなります。
まずはタイムカードや勤怠管理システムを導入し、出退勤時間を正確に把握することが大切です。正確な労働時間の記録は、残業代の適正な支払いにもつながり、スタッフの安心感を生みます。また、変形労働時間制を活用することで、診療時間に合わせた柔軟な働き方が可能となり、法的なリスクを軽減することもできます。
コミュニケーションの場の設置
労務管理においては、スタッフとのコミュニケーションの場を設けることが非常に重要です。医療現場は忙しい日常業務に追われがちで、スタッフ同士や経営者との対話が不足しやすい環境です。しかし、コミュニケーション不足は不満や誤解を生む要因となり、離職や人間関係のトラブルにつながりかねません。
具体的には、定期的な人事面談や全体ミーティングを通じて、スタッフ一人ひとりの意見や要望を直接聞く機会を作ることが効果的です。面談では、日常業務の悩みや不満を共有してもらうことで、早期に問題を把握し、改善につなげることができます。
また、意見を言いやすい環境づくりも大切です。気軽に意見交換ができる場を設けることで、職場全体の信頼関係が深まり、クリニック全体の雰囲気も明るく前向きになります。
専門家との連携が労務管理成功のカギ
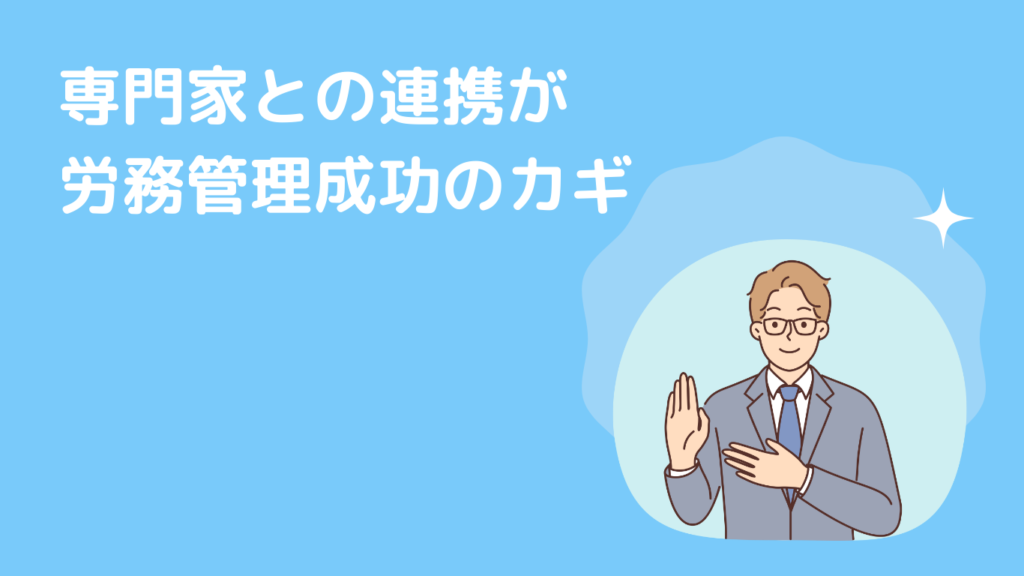
クリニックの経営者が直面する労務管理の課題は多岐にわたります。事務作業の負担、複雑な労務管理、採用活動の難航など、限られたリソースの中で全てを自力でこなすのは困難です。
そこで、事務長代行サービスとの連携が、クリニックの労務管理成功の大きなカギとなります。
労務管理の専門性を活かした運営サポート
事務長代行サービスは、労務管理のプロフェッショナルが貴院のニーズに合わせたサポートを提供します。労働基準法への適正な対応や就業規則の作成・見直し、複雑なシフト管理まで、専門知識を活かしながら確実に対応します。
さらに、労務管理に関する日常的な業務を手放すことで、院長は診療や経営に専念でき、クリニック全体の運営効率が大幅に向上します。
雇用リスクや教育コストの軽減
常勤の事務長を雇用する場合、給与や教育にかかるコスト、そして雇用リスクが伴います。しかし、事務長代行サービスであれば、必要なときに必要な分だけサポートを受けられるため、コストを最小限に抑えることが可能です。
新たに事務長を育成する時間や労力も不要なため、すぐに労務管理体制を整えることができます。
人事・採用活動の支援
スタッフの採用や定着は、クリニックの安定運営に欠かせない要素です。しかし、限られた時間の中で採用活動に力を注ぐことは容易ではありません。
事務長代行サービスでは、採用戦略の立案から面接プロセスの改善、職場環境の見直しに至るまで、人事・採用に関する全面的なサポートを行います。プロの視点から適切な人材確保と定着を支援し、長期的な安定経営をサポートします。
経営者のパートナーとしての相談役
事務長代行サービスは、クリニックの経営課題や労務管理に関する悩みを共有し、具体的な解決策を提案する相談役としての役割も果たします。
管理業務のサポートはもちろん、集患対策や経営改善策のアドバイスまで、経験豊富な専門チームが経営者の右腕として全面的に支援します。
事務長代行サービスを活用することで、煩雑な労務管理を手放し、クリニックの経営と診療に集中できる環境が整います。労務管理の成功は、スタッフの定着や満足度向上、そしてクリニック全体の安定運営につながる重要な要素です。
まとめ

クリニックにおける人事・労務管理は、医療業界特有の課題やスタッフとの信頼関係づくりが鍵となります。突然の退職や労働時間の管理、採用の難しさに悩むこともあるかもしれませんが、ひとつひとつの課題に向き合い、丁寧に対策を進めることで、必ず改善は実現します。
労務トラブルを未然に防ぎ、スタッフが安心して働ける環境を整えることが、クリニック経営の安定化につながります。負担を感じる場合には、事務長代行サービスなど専門家のサポートを活用することで、院長や管理者の負担を軽減しながら労務管理体制を整えることも可能です。
事務長代行サービスなら「レンタル事務長さん」

「レンタル事務長さん」では、クリニックや病院経営における人事、採用、集患、経理などの専門業務をプロフェッショナルに依頼できます。
通常の事務長では対応が難しい複雑な業務も、経験豊富なスタッフがサポート。雇用リスクを避けつつ、クリニック経営者は経営と診療に集中できる環境が整います。
月額95,000円からプランが用意されており、コストパフォーマンスも抜群。サービス内容は柔軟にカスタマイズ可能で、クリニックのニーズに応じたサポートが受けられます。
「レンタル事務長」では、無料相談会を実施中で、わずか30秒で予約完了です。
この機会に、ぜひ「レンタル事務長さん」をご利用ください。

